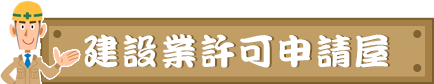分かりにくい経営業務の管理責任者の要件をくわしく解説(第2回)
2 どんな経営経験のある人が、経営業務の管理責任者になれるのか?
経管になるためには、経営経営が必要とされていますが、その経営経験とされる条件が要件として定められています。
その定められている要件をクリアすることができる人が、経管になれるということになります。
続いてその要件をあげていきます。
2-1経営業務の管理責任者となるための要件の構図
経管になるための要件には、次の3つの要件があります。この3つすべてクリアしなければなりません。
要件① 建設業に関する経営経験が十分にあるか?
要件② 要件①の人が、許可申請者の役員や個人事業主として、常勤で勤務しているか?
要件③ 要件①②の人の経営経験や常勤性を証明する確認資料を用意できるのか?
この3つすべてにあてはまる人が自分も含め、今の現状の中にいるのかを検討することになります。
それでは、要件①から順番に検討していきましょう。
要件① 建設業に関する経営経験が十分にあるか?
この経営経験については、状況を分けて考えると分かりやすいと思いますので、以下の3つを順番に検討してみてください。
1 何の業種での経営経験だったのか?
・許可を受けようとしている業種での経営経験
・許可を受けようとしている業種以外での経営経験
2 経営経験を積むのに、どの立場であったのか?
・会社の役員など、個人事業主、令3条使用人であった
・会社の執行役員であった
・経営業務を補佐していた
執行役員や補佐の場合には、少し例外的意味合いが含まれていますので、基本的には、1つ目の「会社の役員など、個人事業主、令3条使用人」であったことが必要であると考えてください。
用語の解説
・会社の役員など
株式会社・有限会社の取締役、委員会設置会社の執行役、合同会社の業務執行社員などのことをいいます。
監査役や会計参与などは含みません。
・令3条使用人
建設業許可における役職の1人です。建設業許可を受ける際に、複数の営業所を設けた場合は、令3条使用人といわれる責任者を置かなければなりません。
いわゆる支店長や営業所長のことをいいます。
令3条使用人として認められるためには、建設業許可を受けた際に、令3条使用人として登録されていなければなりません。
役職上、支店長や営業所長とされていたとしても、令3条使用人になっていない場合があります。
・執行役員
登記はされていないが、取締役会の決議によって具体的な権限が与えられた役員のことをいいます。
・経営業務を補佐していた
個人事業主を配偶者や子息が手伝っていたことをいいます。
事業主の死亡などの急な事態を救済する措置です。
3 経営経験の期間は十分にあるか?
期間が十分とされる基準は、5年以上か6年以上かに分けられています。
・許可を受けようとしている業種で、会社の役員など・個人事業主・令3条使用人として、5年以上の経営経験があれば、許可を受けようとしている業種で、経管になることができます。
・何らかの業種で、会社の役員など・個人事業主・令3条使用人として、6年以上の経営経験があれば、どの業種の経管にもなることができます。
要件② 要件①の人が、許可申請者の役員や個人事業主として、常勤で勤務しているか?
次は、要件①をクリアした人が、常勤で勤務しているのかを、検討していきます。
この要件は以下の2つの両方を満たせば、クリアとなります。
1 申請者の役員や個人事業主になっているか?
この場合の役員は、株式会社・有限会社の取締役、合同会社の業務執行社員などのことをいいます。監査役や会計参与などは含みません。
個人事業主には、支配人も含まれますが、登記されていることが必要になります。
2 常勤で勤務しているか?
常勤とは、休日を除いて毎日一定の時間、実際に勤務していることをいいますから、次のような場合は、常勤とみなされません。
・他の会社で常勤の役員になっている場合
・他の会社で専任技術者になっている場合
・他の会社で宅建取引士のような専任性が必要な役職に就いている場合
・事業主として他に事業を行っている場合
※同一の会社で同一の営業所であれば、専任技術者や宅建取引士などと兼務することができます。
なお、常勤で勤務している期間については規定されていませんので、許可の申請直前に雇用された人でも構いません。
ただ、名義貸しに当たるようなことはしてはいけませんが。
第3回へ続きます。(クリックできます。)