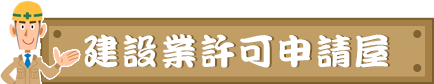建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-17
第25条の16 時効の中断
前条第1項の規定によりあっせんまたは調停が打ち切られた場合において、当該あっせんまたは調停のをした者が同条第2項の通知を受けた日から1月以内にあっせんまたは調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、あっせんまたは調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。
第25条の16 解釈
あっせん、調停が打ち切られた場合に、第25条の15第2項の通知を受けた日から1ヶ月以内に、その目的となった請求について訴訟を提起したときは、時効中断の効力が認められます。
第25条の17 訴訟手続の中止
紛争について当事者間に訴訟が継続する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる
一 当該紛争について、当事者間において審査会によるあっせんまたは調停が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、当事者間に審査会によるあっせんまたは調停によって当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第1項の申立てを却下する決定および前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第25条の17 解釈
第25条の17では、紛争の当事者双方があっせん、調停の利用を希望する場合には、訴訟手続きを中止して、あっせん、調停での解決にゆだねることができると定められています。
・あっせん
対立している当事者に話し合いの機会を設け、原則1人のあっせん委員が当事者双方の意見を聞き、当事者間の歩み寄りを勧めて、1、2回程度で紛争の解決を図る比較的簡略された方法です。
・調停
3人の調停委員が、対立している当事者に話し合いの機会を設け、当事者双方の意見を聞き争点を整理して、当事者間の歩み寄りを勧めたり、場合によっては調停案を作成してそれを受け入れることを勧告します。5、6回程度で紛争の解決を図ります。
あっせんの場合より複雑な紛争の場合に利用されます。
第25条の18 仲裁の開始
審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。
一 当事者の双方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
二 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、審査会に対し仲裁の申請がなされたとき。
第25条の18 解釈
第25条の18は、審査会が行う仲裁はどのような場合に開始されるのかを、定めています。
第25条の条の19 仲裁
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。
2 仲裁委員は、委員または特別委員のうちから当事者が合意によって選定したものにつき、審査会の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員または特別委員のうちから審査会の会長が指名する。
3 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
4 審査会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法の規定を適用する。
第25条の19 解釈
第25条の19は、仲裁手続きが適正に行われるよう、仲裁を担当する委員の選任方法、委員の資格、審査会の行う仲裁には仲裁法の適用があることについて定めています。
建設業許可に関連する法律 建設業法 第3章-17 まとめ
第25条の16
あっせん、調停が打ち切られたときから、一定期間内に、訴訟を提起したときは、時効中断の効力が認められます。
第25条の17
紛争の当事者双方があっせん、調停の利用を希望する場合には、訴訟手続きを中止して、あっせん、調停での解決にゆだねることができます。
第25条の18
審査会は、当事者の双方または一方から、仲裁の申請がなされたときに仲裁を行います。
第25条の19
・仲裁は、3人の仲裁委員で行います。
・仲裁委員は、委員、特別委員のうちから審査会の会長が指名します。
・仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士でなければなりません。
・審査会の行う仲裁については、仲裁法の規定が適用されます。