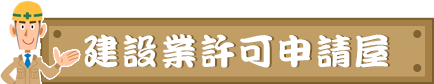建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-1
第3条 建設業の許可
建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める軽微な工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であって、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であって、その営業にあたって、その者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、建設工事の種類ごとに、それぞれ分けて与えるものとする。
3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。
第3条 解釈
建設業を営もうとする者は、一部の軽微な建設工事のみを請け負う事業者を除き、国土交通大臣または都道府県知事から、一般建設業または特定建設業のいずれか一方の建設業の許可を受ける必要があります。
2 建設業の許可は29業種にわけられており、それぞれに対応する建設業の業種ごとの許可を受けることになります。
3 建設業許可の有効期間は5年間です。
4 期限内に更新の手続きをしていても、事務処理上の問題などによって、更新申請から許可通知が届くまでタイムラグが生じてしまう場合があります。
その場合には、期限が過ぎても許可通知が届くまでは、前の許可は有効です。
5 更新後の許可の有効期間も前の許可の有効期限の翌日から5年間です。
6 一般建設業許可から特定建設業許可を受けなおした場合などには、一般建設業許可は効力を失います。
第3条の2 許可の条件
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第3条の2 解釈
建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることを目的として、許可行政庁が一定の場合に、許可について条件をつけたり、変更することを認める規定です。
建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図ることが目的なので、「不当な義務を課することとならないもの」でなければなりません。
本条が追加された際に、建設業許可の簡素化・合理化の一環として、許可の有効期間が3年から5年に延長されています。
第4条 附帯工事
建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。
第4条 解釈
建設工事ごとに許可が必要であることをあまり厳格に適用してしまうと、かえって不便になってしまうため、許可を受けた建設業以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に関連した工事に附帯する工事であれば、請け負うことができることを規定しています。
・附帯工事とは
1 メインの工事を施工するために必要な工事。
2 メインの工事の施工によって必要になった工事
3 それ自体が独立の使用目的に供されるものではない工事
をいいますが、附帯工事であっても軽微な工事でないならば、自ら施工する場合には技術者の配置は必要ですし、他者に施工させる場合にはその付帯工事に係る許可を受けている建設業者に施工させなければなりません。
・附帯工事の判断基準
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行などを基準として、その建設工事の準備、実施、仕上げなどにあたり、一連の工事または一体の工事として施工することが必要であるか、あるいは相当であると認められるかどうかを総合的に検討するとされています。(国総建97)
建設業許可に関連する法律 建設業法 第2章-1 まとめ
第3条が定めている建設業の許可についてまとめます。
・建設業の許可
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、「建設業の許可」を受けなければならない。
・許可行政庁
①国土交通大臣
②都道府県知事
・許可業種
①29業種に分けられている。
②営業する業種ごとに許可を取得する必要がある。
③同時に二つ以上の許可を受けることができる。
④業種を追加することもできる。
・有効期間
建設業の許可は5年間有効で、5年ごとに更新が必要。
・許可の区分
許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業または特定建設業の許可を受けなければならない。
第3条の2には、許可行政庁が一定の場合に、許可について条件をつけたり、変更することを定めていますが、これは不当な義務を課することとならないものでなければなりません。
第4条は、許可を受けた建設業に関連した工事に附帯する工事であれば、許可がなくても請け負うことができることを定めています。