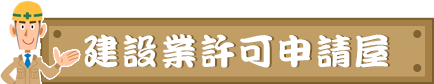建設業許可の経営事項審査を解説
経営事項審査とは?
経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力などを判断するための資料として、その建設業者の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。
公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。
一般に「経審」と呼ばれており、経審を受けた建設業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得することが、目的になります。
そして、その「総合評定値通知書」を提出することが、公共工事の入札に参加するための要件の一つです。
経営事項審査の基準にされる日
審査の基準日は、申請する日の直前の事業年度の終了日(決算日)です。
法人合併や営業譲渡が行われた場合には、当該合併日や営業譲渡日を審査基準日として、経営事項審査を受けることができます。
経営事項審査の有効期間
公共工事について発注者と請負契約を締結できるのは、結果通知書を受け取った後、その経営事項審査の審査基準日から1年7か月までに限られています。
公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があり、遅れれば遅れるほど、公共工事の契約時に有効な結果通知書のない可能性が高くなり、契約を締結できなくなる場合があります。
経審を受けるため前提条件
建設業許可を受け、決算変更届を提出していることが、経審を受けるための前提条件になります。
経審の構成
経審は大きく分けて「経営状況分析申請」と「経営規模等評価申請」の2種類の申請をすることになります。
1 経営状況分析申請
経営状況分析申請では、建設業者が決算終了後に提出した決算書から、その建設業者の経営状況を数値化し、その数値を一定の算式に当てはめて、評点が出されます。
そして、その経営状況の評点が記載されている、「経営状況分析結果通知書」を取得することが、経営状況分析申請の目的になります。
2 経営規模等評価申請
経営規模等評価申請では、建設業者の経営規模や技術力、社会性などが数値で評価されます。
この申請をする際に、先の「経営状況分析結果通知書」を合わせて提出することにより、経営状況と経営規模の両方から算出した「総合評定値通知書」を取得することができます。
経審の大まかな流れ
1 決算終了後、決算変更届の届出
↓
2 登録分析機関へ経営状況分析申請し、「経営状況分析結果通知書」を取得する
↓
3 「経営状況分析結果通知書」とともに書類を揃え、経営事項審査申請
↓
4 「総合評定値通知書」を取得する
↓
5 入札参加資格登録申請
入札参加資格登録は2年に1回だったりしますが、経審は毎年継続して受けることが必要です。
建設業許可の経営事項審査を解説 まとめ
経営事項審査とは、業者の施工能力や財務の健全性、技術力などを判断するための資料として、その業者を総合的に評価するものです。
公共工事の元請業者となるためには、経営事項審査を必ず受ける必要があります