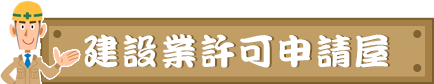建設業許可に必要な専任技術者とは
簡単に言えば、建設業許可を受けようとする建設業に関して、専門的な技術的知識や経験を持つ人のことです。
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに常勤する「専任技術者」がいないといけません。
専任とは
その営業所に常勤して、専らその職務に従事することを要する者のことをいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として認められます。
次のような者は、原則として「専任」とはみなされません。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・他の営業所において専任を要する者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士など、他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者など、他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
・給与の額が最低賃金法に基づく額を下回る者
「専任技術者」と認められるための要件
一般建設業許可の場合は
①大学又は高校で許可を受けようとする建設業に関連する学科を卒業後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験がある者
②許可を受けようとする建設業で、10年以上の実務経験がある者
③一定の国家資格がある者(1級又は2級)
特定建設業許可の場合は
①一定の国家資格がある者(1級のみ)
②一般建設業許可の条件①②③のいずれかに該当し、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある者
③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
ただし、指定建設業については、①③に該当する者でなければなりません。
これらのいずれかに該当し、それを証明する確認書類を用意できれば、「専任技術者」として認められます。
指導監督的な実務の経験とは
建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
指定建設業とは
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種のことをいいます。
専任技術者に関しての注意点など
専任技術者は、同一の営業所内において、各業種につき、それぞれ1名ずつ担当することとなり、複数の専任技術者が同じ業種を担当することはできません。
営業所における専任の技術者は、営業所に常勤して専らその職務に従事することが求められていますが、下記の要件を全て満たす場合には、営業所における専任の技術者は、現場の専任を要しない主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者等」という。)となることができます。
①当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること。
②工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で、常時連絡のとれる体制にあること。
③所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
④工事現場の専任を要しない監理技術者等であること。
工事現場の専任を要しない監理技術者等とは、公共性のある工作物に関する重要な工事(工事の請負代金の額(税込)が、3,500万円(建築一式工事にあっては7,000万円)以上のもの。)現場以外に配置されるものをいいます。
専任技術者の実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、または現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれます。
また、実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ、合算した期間とされます。
経験期間が重複しているものにあっては、原則として二重に計算されません。
ただし、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとされます。
電気工事や消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法などにより電気工事士免状や消防設備士免状などの交付を受けた者などでなければ、経験期間に算入されません。
また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業もしくはとび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で請け負ったものに限り、経験期間に算入されます。
経営業務の管理責任者の要件に該当する人が専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内であれば、兼任することができます。
専任技術者の要件は、許可を受けようとする建設業について、専任技術者としての基準を満たしている人を1つの建設業ごとに、それぞれ個別に置いていることを求めるものではありません。したがって、2以上の建設業について許可を行う場合において、1つの建設業につき1人の専任技術者を求めているのではなく、複数の業種を1人の専任技術者が担当することが可能です。
ただし、2以上の建設業について実務の経験を要する場合、それぞれ異なる期間であることが必要です。経験期間が重複しているものにあっては二重に計算されません。
平成28年6月1日に、既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている人については、平成33年3月31日までの間、「解体工事業」の技術者とみなされます。
ただし、経過措置によって「解体工事業」の許可を受けた場合には、経過措置期間内に「解体工事業」の技術者としての要件を満たすか、要件を満たしている技術者に変更する必要があります。
一般建設業の専任技術者の要件に該当するための実務経験の期間の全部又は一部が、指導監督的な実務経験の期間の全部または一部と重複している場合には、当該重複する期間を一般建設業の専任技術者の要件に該当するための実務経験の期間として、算定すると同時に、指導監督的な実務経験の期間として算定することができます。
なお、指導監督的な実務経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ、合算した期間とされます。
経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算できません。
ただし、平成28年5月31日までに、とび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業許可と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとされます。
なお、電気工事や消防施設工事については、それぞれ電気工事士法、消防法などにより電気工事士免状や消防設備士免状などの交付を受けた者などでなければ、経験期間に算入されません。
また、建設リサイクル法施行後の解体工事の経験は、土木工事業、建築工事業もしくはとび・土工工事業許可または建設リサイクル法に基づく解体工事登録で請け負ったものに限り、経験期間に算入されます。
建設業許可に必要な専任技術者とは まとめ
「建設業許可の専任技術者」とは
建設業許可を受けようとする建設業に関して、専門的な知識や経験を持つ人のことで、
建設業許可を受けるためには、営業所ごとに常勤する「専任技術者」がいないといけません。
専任技術者の要件は
一般建設業許可の場合は
①大学又は高校で許可を受けようとする建設業に関連する学科を卒業後、大卒で3年、高卒で5年以上の実務経験がある者
②許可を受けようとする建設業で、10年以上の実務経験がある者
③一定の国家資格がある者(1級又は2級)
特定建設業許可の場合は
①一定の国家資格がある者(1級のみ)
②一般建設業許可の条件①②③のいずれかに該当し、4,500万円以上の元請工事で2年以上の指導監督的な実務経験がある者
③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者
ただし、指定建設業については、①③に該当する者でなければなりません。
これらのいずれかに該当し、それを書類上で証明できれば、「専任技術者」として認められます。